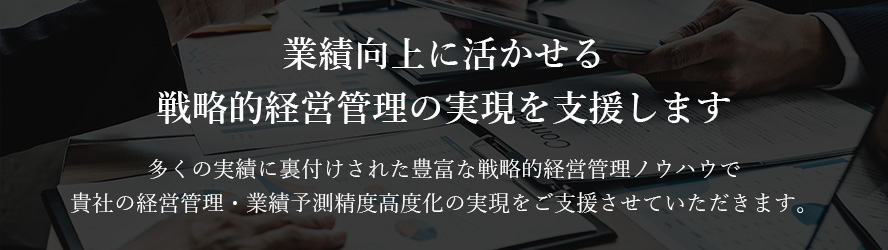日本企業のIRレベルはなぜ低いのか? 欧米に学ぶ、CFOに求められるスキルとは
日本企業のIRレベルはなぜ低いといわれているのでしょうか。
本記事では、日本と欧米企業のCFOの違いと共に、CFOに求められるスキルについて解説します。
年度と数値を変更するだけの決算報告
以前、知人からこんなことがあったことを聞いたことがあります。
彼は、上場企業などが提出する有価証券報告書の英語版の翻訳に触れる機会がありました。
ある企業の英語版の有価証券報告書を見ていて、あきらかな誤訳を見つけました。その誤訳は前年度にも使われている表現だったそうです。
「訂正を出しましょうか?」とその企業に問い合わせたところ、
「もう一度全文の英訳を精査しなければいけなくなるので、そのままで結構です」という回答だったそうです。
えっ、間違ったままで・・・
前年度も類似の表現を雛形のように使用して、極端に言うと、年度と数値を変更するだけで対応しているのでしょう。英訳に誤訳があったとしても訂正にかかる手間、外部委託コスト、そしてさらなる間違いが生じる可能性を気にして、外注した翻訳担当任せになってしまっているのではないでしょうか。ということは、せっかくの決算内容、終了した事業年度の社員のみなさんの事業経営の取り組みを、株主をはじめ社外に対して、知っていただくという上場企業としての、せっかくの機会を逸していると言わざるを得ません。
「定型情報」から踏み出せない財務経理部門
それでは、欧米企業の場合はどうでしょうか?
多くの企業が、自社の取り組みや業績をいかに伝えるかを工夫しています。アニュアルレポートは、その年の事業活動の特徴を理解してもらうために、毎年デザインや、単に何年度のアニュアルレポートだけではなく、その年のキーメッセージを表題にするなど、オリジナリティあふれた構成になっています。
日本企業での毎年同じようなメッセージとフォーマットで決算説明資料を作成しているのとは大きな違いがあります。背景には、日本企業は監査法人のチェックを通った、ある意味「お墨付き」をもらった安心できる情報のみを開示しようと思っているかのような、定型情報から財務経理部門が踏み出せないという極めて保身的なカルチャーがあるのではないでしょうか?
終身雇用制が徐々に薄れてきているとはいえ、新しいことや従来から変わったことをすることで、マネジメント層から非難をされたり、準備していない質問を社外から受けた際に適切に対応できないかもしれないという不安があるのかもしれません。
自社の取り組みや業績をいかに伝えるかを工夫する欧米企業
一方、欧米企業のCFOたちは、自社の事業経営、業績をいかに株主、株式市場により理解を深めてもらえるかに、常に苦心しています。そのために、他社がやっていない観点で分析をしたり、資料の工夫をしています。説明(プレゼンテーション)においても、自分のフィナンシャルマネジメントスキルを知ってもらうためのデモンストレーションのように工夫をしています。
CFOたちは意識しているかどうかわかりませんが、自社の理解を深めるだけではなく、自信のスキルを知ってもらえる機会にもなっているといえます。
IR(インベスターズ リレーションシップ、株主に対する情報開示)活動やアニュアルレポートはCFOのスキルの広告塔のような意味合いも存在するように感じます。
他部門に積極的に関与する欧米のCFO
これらの財務経理領域に加えて、CFO、各子会社CFOやフィナンシャルコントローラーと言われるポジションのひとたちは、社内のあらゆる部門に対して、全社ベースの企業価値・業績向上のために、積極的に関与・コメントをし、他部門の責任者からすると「介入」をします。
たとえば、子会社のCFOが営業部門が行う薄利多売で売上はあがるが収益性の低い事業を、短期間シェアを獲得して、その後アップセルをするなど戦略的計画もないまま放置していたします。
こうした状態を、本社CFOは管掌領域外だからと許容するかというと全く逆で、評価を落とすか、解雇されるくらいの厳しい職務レベルを求められます。
営業部門に対しては価格戦略やマーケティングアプローチに対して、製造部門であれば在庫削減や原価低減など積極的に関与しています。また、設備投資については必要性のみならず、全社のバランスシート管理、ROIの維持向上の観点から、投資計画自体の適否にコメントをしたりします。CEOが賛成でも、財務視点でCFOが反対すると、見直しを求められたり承認されないというケースも珍しいことではありません。
このような活動の裏付けがあるため、決算書に現れる財務数値の大小比較だけではなく、その背後の各事業部門の取り組み、難易度の理解が伴ってきます。どの観点、どの指標を用いて過年度分析を行い、説明をするかはCFOの腕のみせどころであり、本質的な自社の事業の理解度が問われます。
KPIは一般的なものではなく、社内の業績管理に適しているもの、社外への説明に適しているものを、CFOが自社でオリジナルに定義していることも多くあります。
社員が頑張った成果を一般的な他人軸ではなく、自社軸で説明をすることの必要性の認識と、それを実行する勇気が求められるということの表れかと思います。
CFO出身のCEOが多い欧米企業
欧米企業には、CFO経験者のCEOが多く見受けられます。
経営戦略、リスクを理解して、経営陣の一角として行動し、上場企業としてフィナンシャルマネジメントをリードし、社外への発信を担ってきたCFOはCEO候補としては適任者の一人となるということでしょう。
日本企業の終身雇用的な働き方と異なり、このように分析力が高く、株主の理解度を高めるプレゼンテーションスキルの高いCFOたちは、他社の経営者も魅力を感じ、ヘッドハンティングでより高額報酬がもらえる大企業に転職したりしています。もちろん転職しなくても、自社のCEOや株主の評価も高いものが得られるでしょう。
リスクのある株式投資をしている株主が求めていることは、経営陣がどういう経営課題、成長分野を認識して、どのように取り組んだのかという「よりリアルで納得感のある情報提供」です。それがたとえ失敗のようでも、そこから学んだ知恵を活用して、より具体的に業績向上に向けて取り組んでいる、というイノベーティブな姿勢を感じれば、将来の企業価値向上の期待から、株式の購入を考えるという流れにもつながるでしょう。
社員が努力した成果を適切に表現して理解を得る
以前、プロフォーマ財務諸表という情報開示のしかたが注目されました。
過去に撤退した事業、売却した事業などは、単純に各事業の合計数値を対前年度比較をして説明をしても、事業の成長性や改善、悪化の説明が難しいことがあります。
そこで、会計監査の対象となる財務諸表や数値ではなく、経営実態をより良く説明するために仮の「〇〇がなかったとしたら」という仮説のもとに、数値比較や説明をするということをするCFOたちが多くいました。
これには深い経営戦略の理解度、高度な分析、説明能力とともに、高い倫理観も求められます。
たとえ会計監査の対象外でも、虚偽報告や粉飾に近い、財務諸表、アニュアルレポート利用者をあざむくような状況と紙一重でもあります。そこで、プロフォーマ財務諸表の利用方法については、制約を課されるようになってきました。
しかしながら、会計基準に則った財務諸表をベースにしていては、せっかく社員が1年間努力をした成果が適切に表現しきれないことがあります。そのような時にどうすれば、より適切な理解を得られるかを工夫するのはCFOの職務だと思います。
最後に 日本に求められる「CFOチーム」
日本と欧米の文化の差はあり、いちがいに日本が劣っているなどと申し上げるつもりはありません。日本の良さを活かして、自社の取り組みをより多くの人に、より適切に理解してもらうことが大切です。そのためには、従来の慣行の殻を破れないサラリーマンCFOでは実現することはできません。
高度な分析能力を活かし、プレゼンテーション能力を高めて、事業の成果を世に問う「プロフェッショナルなCFO」が、成長が鈍化した今の日本において求められるのではないかと思います。
日本企業はミドルマネジメントが強いと言われます。
CFOが個人技でこの状況を実現するだけでなく、財務経理部門、経営管理部門を含めた「CFOチーム」を組織的に強化し、チームでの対応力を高めることが日本においてはマッチしていると思われます。そして同時に次世代のCFOを育成するような仕組みの導入も考えられていいのではないかと感じます。